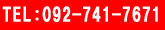専門業務型裁量労働制IT企業
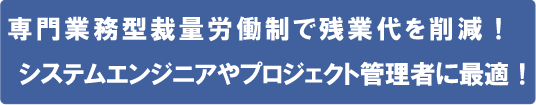 IT企業において、プロジェクトマネージャーやシステムエンジニアなどのように、労働時間で残業代を出すのではなく、成果によって評価を行って、成績優秀者については賃金アップやボーナスアップ、成績が悪い者についてはその逆を行いたい場合が多々あります。 そもそもIT企業には、労働時間のみで残業代を算出するという方法は、実態にあっていません。作業効率が良い社員は残業をしなくても作業が終わり残業代が不要で、作業効率が悪い社員は残業をしてやっと作業が終わり残業代が必要という現状では会社としては納得がいかないものです。 そこで、登場するのが「専門業務型裁量労働制」という制度です。 |
| 専門業務型裁量労働制とは?? | ||||||||||||||||||
| 専門業務型裁量労働制というのは、簡単に言うと「例えば1日あたりの労働時間を実際の労働時間に関わらず、9時間労働したとみなす」といった制度です。 もちろん、IT企業の社員が全員対象となるわけではありませんが、この制度を有効に活用することによって、労務管理や人事考課の幅が広がるのは間違いありません。 また、実際に制度を導入するにはいくつか条件があって、以下の内容を労使協定で定める必要があります。
これらの内容を協定書にまとめて、労使協定を結び、労働基準監督署に協定届を提出すれば、導入手続は完了となります。 |
| 専門業務型裁量労働制を導入した後の、残業代について |
| 専門業務型裁量労働制を導入した後の、残業代の取り扱いについては、明確な通達などがありません。 そのため、原則としては、通常の残業計算を行うこととなり、雇用契約の内容や就業規則の内容が大きく影響します。 雇用契約に書かれてある金額が、みなし時間分も含むのか、含むのであれば、それはいくらなのか。含んだとしても、割増相当分はどうなるのか。など、非常に高度な対応が必要となります。 上手く定めれば、残業代を削減することもできるので、ぜひとも導入したいところですが、その複雑ゆえに悩んでいる会社もあると思います。 当事務所では、その様な会社様たちをサポート致しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 協定書の作成、提出や、導入に向けて就業規則の修正などトータルサポートを行っています。 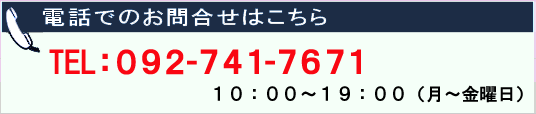 |
| 専門業務型裁量労働制導入の流れ |
●初回打ち合わせ まずは、現状の確認をいたします。現在の従業員がどのような働き方をしているか、勤務時間の実態がどうなっているかなどを確認いたします。 まずは、現状の確認をいたします。現在の従業員がどのような働き方をしているか、勤務時間の実態がどうなっているかなどを確認いたします。●現状の運用などを確認  現在、勤務時間の把握方法や残業の計算方法をどのように行っているかの詳細を伺います。 現在、勤務時間の把握方法や残業の計算方法をどのように行っているかの詳細を伺います。 |

| 資料の整理と制度導入が可能かを調査(1〜2週間程度) |
●出勤簿と賃金台帳を分析 お預かりした帳簿を分析して、現状の運用をなるべく変えずに専門業務型裁量労働制が導入できるかどうか、そしてサービス残業代が削減できるかどうか、もしあればそれはいくらかなどを分析します。 お預かりした帳簿を分析して、現状の運用をなるべく変えずに専門業務型裁量労働制が導入できるかどうか、そしてサービス残業代が削減できるかどうか、もしあればそれはいくらかなどを分析します。●専門業務型裁量労働制のシミュレーション  当事務所で分析した結果を踏まえて、実際に専門業務型裁量労働制を導入した際のシミュレーションを行います。 当事務所で分析した結果を踏まえて、実際に専門業務型裁量労働制を導入した際のシミュレーションを行います。 |

| シミュレーション結果の説明と原案の提示 |
●シミュレーション結果についての説明 当事務所で行ったシミュレーション結果の説明を行います。どのようにすればどのような結果が出るかを明示いたします。 当事務所で行ったシミュレーション結果の説明を行います。どのようにすればどのような結果が出るかを明示いたします。●専門業務型裁量労働制の協定原案を提示  シミュレーション結果を元に、現状で考えられるベストの提案を行います。 シミュレーション結果を元に、現状で考えられるベストの提案を行います。そして、その提案を実現するためには、どのようなことを行う必要があって、どのような流れになるかを御説明いたします。 |

| 従業員への説明、協定内容について調整(2回から3回程度) |
●従業員への説明 専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定を結ぶ必要がありますので、この協定内容を従業員と詳細まで話し合いをします。 専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定を結ぶ必要がありますので、この協定内容を従業員と詳細まで話し合いをします。●合意内容を協定書にする  従業員との打合せが終わり、合意に達したら、その内容を協定書に落とし込みます。 従業員との打合せが終わり、合意に達したら、その内容を協定書に落とし込みます。 |

| 必要により、就業規則・賃金規程の修正(1〜2ヶ月程度) |
●必要により、修行規則・賃金規程の修正 専門業務型裁量労働制を導入するにあたり、制度に対応する部分の就業規則や賃金規程を修正する必要がある場合があります。 専門業務型裁量労働制を導入するにあたり、制度に対応する部分の就業規則や賃金規程を修正する必要がある場合があります。●修正した規程の説明  当事務所が修正した就業規則・賃金規程と雇用契約書について、説明を行います。各条文について、この条文が必要な理由など詳細をご説明します。 当事務所が修正した就業規則・賃金規程と雇用契約書について、説明を行います。各条文について、この条文が必要な理由など詳細をご説明します。 |

| 労働組合・従業員代表と協定を締結、専門業務型裁量労働制の本番稼動 |
●労使協定を締結 労働組合・従業員代表と労使協定を締結、そして労働基準監督署へ届出を行い、専門業務型裁量労働制の本番稼動をします。 労働組合・従業員代表と労使協定を締結、そして労働基準監督署へ届出を行い、専門業務型裁量労働制の本番稼動をします。●本番稼動後  いよいよ専門業務型裁量労働制の本番稼動の開始です。本番稼動後は、制度が正しく運用できるよう、勤務内容・健康状態の把握に注意してください。。 いよいよ専門業務型裁量労働制の本番稼動の開始です。本番稼動後は、制度が正しく運用できるよう、勤務内容・健康状態の把握に注意してください。。上手く運用することで、仕事をしやすくしたり、サービス残業を削減するという大きな効果を生みます。その結果として会社に多くの利益が出た際には、ぜひとも社員の皆さんにボーナスを支給して還元してあげてください。 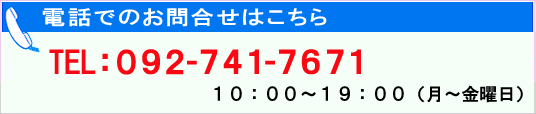 |